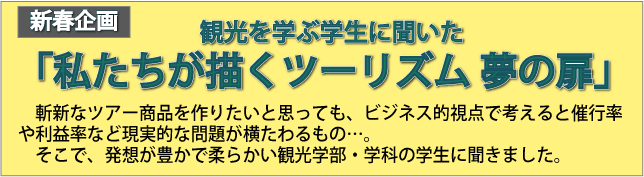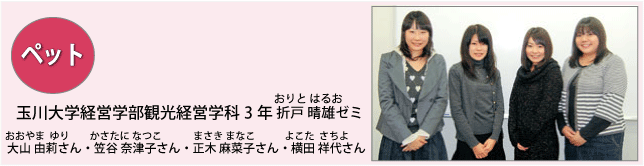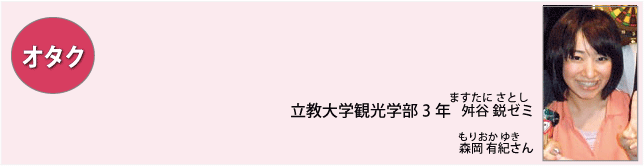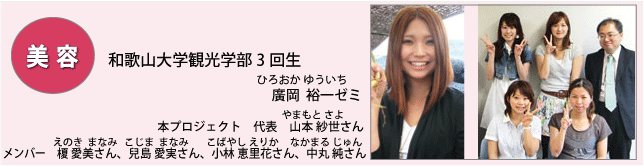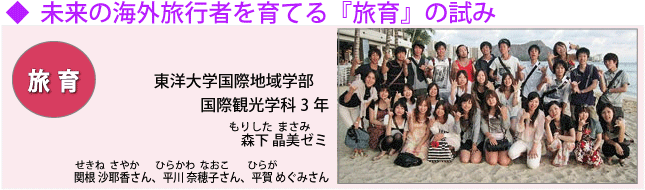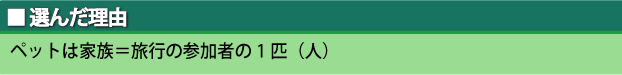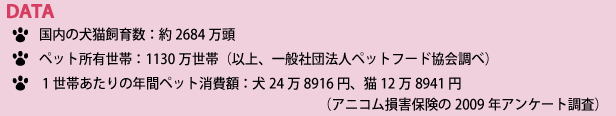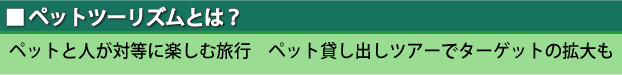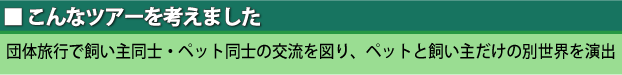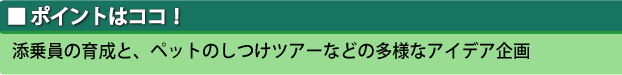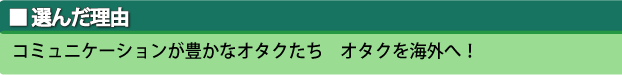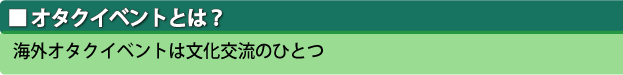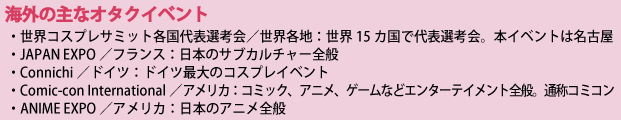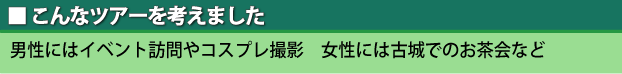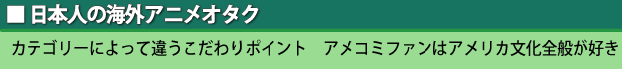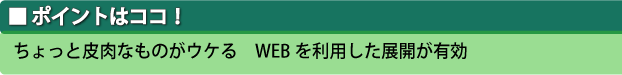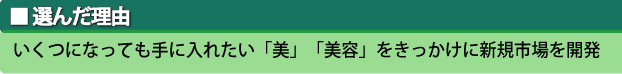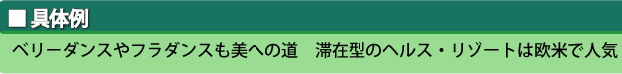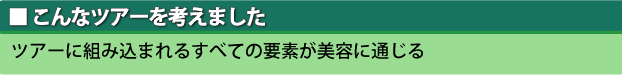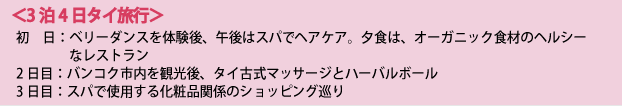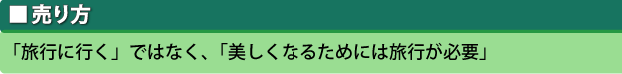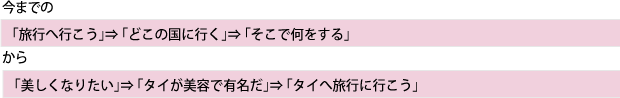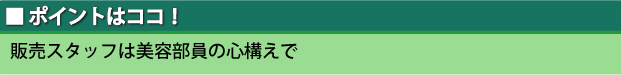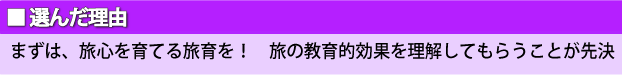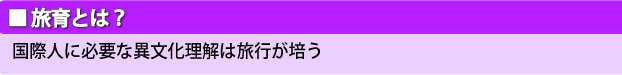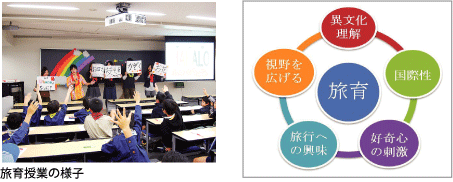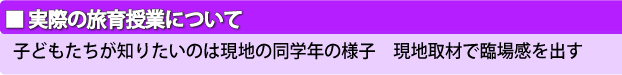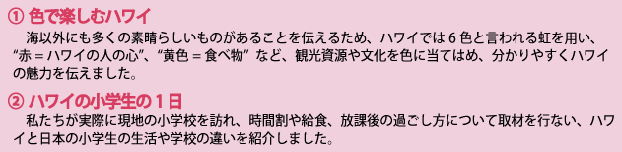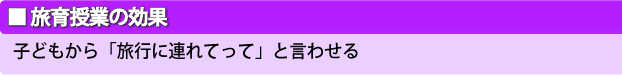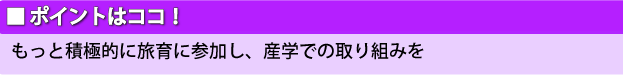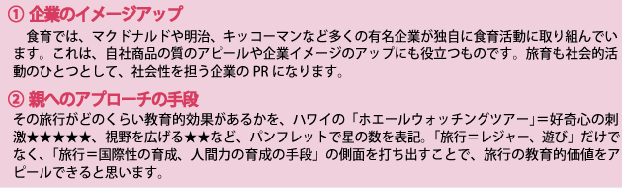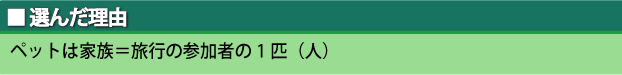
ペットは日本の家庭に広く定着し、国内の犬猫飼育数は約2684万頭(一般社団法人ペットフード協会調べ)。日本の15歳未満の子どもの数の倍以上になっており、もはや飼い主と一緒に人生を歩む、かけがえのないパートナーとなっています。1世帯あたりの年間ペット消費額は、犬24万8916円、猫12万8941円と、この不況下でも2008年度から20%以上増加(アニコム損害保険の2009年アンケート調査)しており、ペットビジネスの規模は無視できないものです。車での愛犬同伴旅行を一度以上体験している飼い主は7割近くになっており、経験のない飼い主をみても約7割は「いつか一緒に旅行してみたい」という願いを抱いています(ペット総研調査)。このようなニーズがあるにもかかわらず、旅行会社のペット同伴旅行はあくまでも「ペットはペット」としてしか捉えておらず、「家族の一員」として捉えるものは少ないのが実情です。
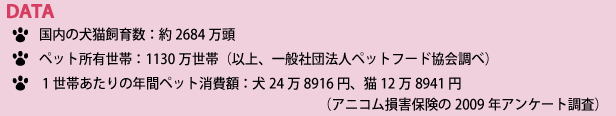
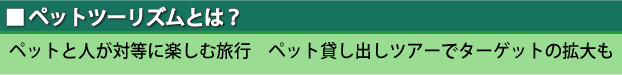
そこで私たちは、既存の「わんちゃんと行くバスツアー」など、人が中心となっているツアーよりも、ペットと人が対等の立場で心から楽しめるツアーが必要と考えました。開放的な土地で過ごせば、人間同様にペットのストレスも解消され、ペットと家族の絆もより深まるのではないでしょうか。そこに、ペットツーリズムの実現性が大きく広がっていると考えます。
また、住宅環境や家庭の事情により飼うことがでない人たちのために、「ペット貸し出し制度」を設けることで、ターゲットの拡大に繋がるでしょう。
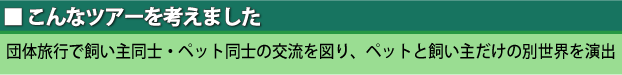
あえて、個人旅行ではなく団体旅行を推進します。団体旅行は、バスや列車、フェリーを貸し切り、ペットと飼い主だけの別世界を作ることができます。交通機関の中でイベントを開催することで、ペット連れ旅行者同士の交流も可能。ペットが
ゲージなしで自由に動き回ることができるようになれば、移動しながら楽しめる「動くイヌ・ネコカフェ」が実現します。クルーズなら、飼い主同士のコミュニケーションを船内で図ることができ、ツアー本体をより楽しめます。非日常空間を演出するなら、クルーズは有効な移動手段だと思います。
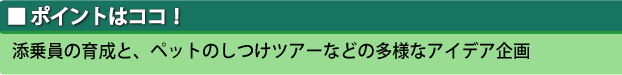
ペットツーリズムで重要となるのが添乗員の存在です。添乗員には、旅行に参加する飼い主の不安を解消する相談役として、動物の正しい知識が求められます。また、旅館やホテルを利用する際のマナーを熟知し、飼い主に正しい知識を与える役割を担うことも期待されます。つまり、ツアー管理だけでなく、ペットインストラクター、エンターテイナー、ペットシッターなど、幅広い知識が求められるため、資格制度化への検討も必要でしょう。資格を持つ添乗員の存在が安心・安全を与えるだけでなく、ペットの排泄物や衛生面などの問題点に対する解決策の徹底にもなるため、添乗員の育成は重要なポイントです。そして、飼い主に正しいマナーを身につけてもらうための講習会を開くなど、受け入れ先の宿泊施設と旅行者、旅行会社との間に信頼関係を築くことも重要です。
また、ペットを旅行の参加者と考え、さまざまな切り口からの企画立案が求められます。他のペットや飼い主との交流につながるツアー、新たにペットを飼い始める人のためにペットインストラクターを講師に招いた「しつけツアー」など、多様なアイデアを立案し、商品化実現に向けて取り組むべきと考えます。
|