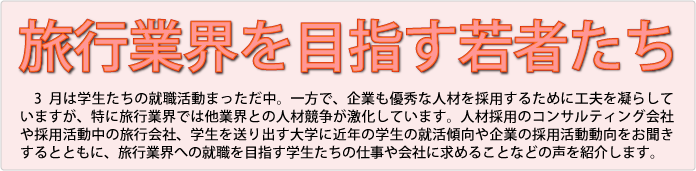|
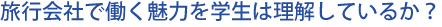
以前は観光学科=旅行のイメージがありましたが、今はホスピタリティ系の学科や、社会の問題を解決するための学問として観光学そのものの概念が広がりました。ビジネスとしての観光や学問としての観光を学んだ視点から旅行業界を見ると、旧来型の旅行業のままでは魅力が分かりにくいのかもしれません。大学で旅行業について学ぶと、添乗員の待遇が厳しいことや、ツアーの企画といっても制約が多く、実現可能なものを作ろうとすると「企画はそれほど楽しいものじゃない」ことに気づいてしまうんですね。学生にとって旅行会社で働く魅力が感じられなくなってしまっているのでしょう。

以前の観光学科の学生達の多くは就職希望先として旅行会社を中心に考えていたものでしたが、観光系学部として学習分野が広がると、ホテル業界に就職を希望する学生が増えているようです。これはホテル業界がインターンシップに非常に積極的なことも関係があるのではないかと感じています実際に社員が働いている現場を見ることで、その業界や会社にどんな人材が向いていて、どういう人材が求められているのか、そこで自分がどのように働くことができるのか、働きながら何を身につけられるかがイメージしやすくなるのだと思います。翻って旅行業界は、ネットで旅行の手配を終わらせる昨今の学生にとって旅行会社がそれほど身近ではなく、どんな仕事をしているのかがイメージしにくいのではないでしょうか。しかも、旅行業界のことを学んだ観光学科の生徒においても、在学中に一生懸命とった資格を旅行会社の社員が参加する授業や業界セミナーなどでいとも簡単に「資格を持っていても採用に役立たない」と言われてしまう。そうすると、今まで自分が何のために勉強をしてきたのか、その意義を見出せなくなり、旅行会社で何ができるのかが見えてこないのだと思います。
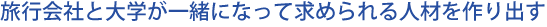
観光(=旅)は、各自に与える多様な効果と社会を変える大きなインパクトを持っているはずです。そのためにどのような人材育成を行うのか、大学のカリキュラム編成にもさらなる改善が必要です。一方で業界には、どういう人材が欲しいのかを大学側や学生に発信してほしいと思います。「人間力」では抽象的です。例えば、学校の枠を飛び出して観光の活動をしている日本学生観光連盟のような、組織的な活動の運営に携わったことがあるなど、学生が想像しやすいものを発信していただきたいですし、それを我々大学関係者と一緒に作っていけたらと思います。
|