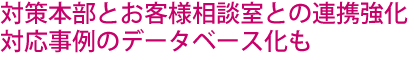|
3月号インデックス│特集1│特集2│旅の力│JATA NOW│ Cafe de JATA │添乗員のための旅行医学│バックナンバー |
| |
| P2 【特集/旅行会社のリスクマネジメント】 |

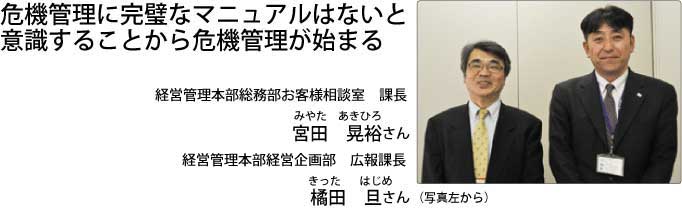
当社では以前から危機管理(リスク管理)対応マニュアルはありましたが、2003年のイラク戦争をきっかけに、今後、海外における事故だけではなく企業経営に影響するような幅広い分野でのリスク発生に対する体系立った危機管理が必要であると考え、対応マニュアルの整備に着手しました。現在では、事件・事故、自然災害、食中毒、新型インフルエンザといった感染症のほか、システム関係のトラブルや情報漏えい、テロ、反社会的勢力に対する対応など、想定されるリスクをジャンル分けして作成しています。
ひとたび事件や事故、トラブルが起きれば、お客様相談室にも電話が集中します。それが大きなリスクであれば、対策本部を設置し連絡系統が一本化され、そこを起点に社内外に対し会社としての明確な対応や情報が発信されます。お客様相談室としても本部と連絡を密にとりながら的確な解答ができます。CS的な観点から言いますと、各部署で言っていることが異なることが一番混乱をまねく原因となります。
マニュアルを整備するに当たり、海外にグローバル展開する企業や食品・流通など異業種のリスク管理もリサーチし、旅行業にも参考となる部分は積極的に取り入れました。基本となるものを作成し、それに各部署の意見なども取り入れ随時更新を重ねることで、現場の実態に合うものになりました。しかし、危機管理対応で大切なことは、マニュアルを作って安心してしまわないことです。1年に1回はマニュアルの内容や連絡網の確認を行うほか、ゴールデンウィークや年末年始など長期の休み前にも必ず連絡網のリストを見直してもらっています。さらに重要なことは、いかにマニュアルがしっかりできていても「想定外の事態は必ず起こる」と考えて対応することだと思います。完璧な対応マニュアルなどないと考えることから危機管理は始まっています。事態をいかに的確に把握し、情報を社内で共有した上で、どう迅速かつ適切に対応するかを常に意識することが大事だと考えます。 |
●事件・事故 |
 |
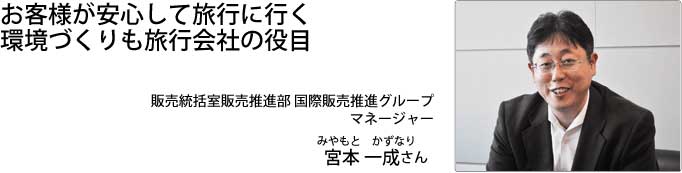
2011年4月出発の商品から、ANAハローツアーの全方面、全コースに、海外旅行保険を組み込みました。ANA’sシリーズと旅ドキシリーズでは補償内容に差がありますが、全商品に海外旅行保険を組み込むのは業界初だと思います。もともと当社では、1993年から現地でのケガ・病気の治療費を50万円まで補償するサービス(ハローアシスト)を行っていますが、今回のサービスは、これを拡充させたものです。
この事故を機に、社内で経営企画部や販売統括、CS推進などのほか、総務などの管理部門を含めた横断的なプロジェクトチームを立ち上げました。当初は、いかに任意の海外旅行保険の付保率を高めるかを中心に話を進めていましたが、いろいろな面から対策を検討する中で、「ハローアシストを拡大する形で何かできないか」との意見が出て、全商品に海外旅行保険を組み込む「あったかサポート」を開始することにしました。
ANA’sシリーズでは治療・救援費用の保険金額を無制限、賠償責任の保険金額を1億円にするほか他、死亡補償、携行品損害なども付いていますが、旅ドキシリーズは治療・救援費用と賠償責任のみ付保し、保険金額をそれぞれ1億円としました。お客様サービスの一環としては十分な補償額になっていると思いますが、それでも決して任意の保険に入らなくていいというものではありません。この補償はホールセラーとしてのお客様に対するサービスと考えており、足りない分は任意で海外旅行保険に加入していただくことが必要で、お客様には引き続き保険を勧めていただきたいと思います。補償内容については、任意の保険同様に補償対象の有無があります。今回の商品発売とあわせ専用ダイヤルを用意してお客様や販売する旅行会社からの問い合わせに対応します。 |
●経営企画部 |
 |
| |
|
3月号インデックス│特集1│特集2│旅の力│JATA NOW│ Cafe de JATA │添乗員のための旅行医学│バックナンバー |
Copyright (c) 2011 Japan Association of Travel Agents. All right reserved.